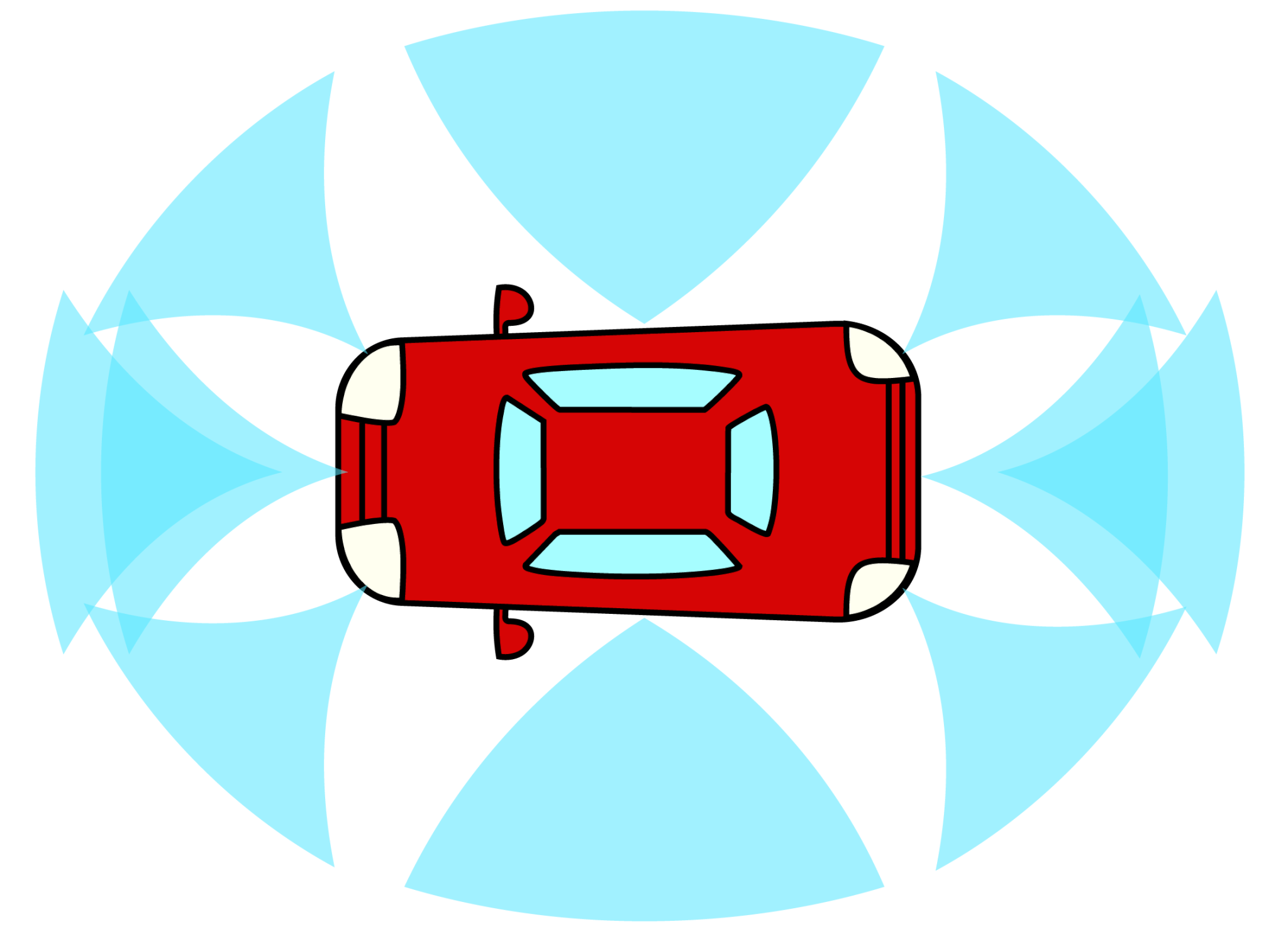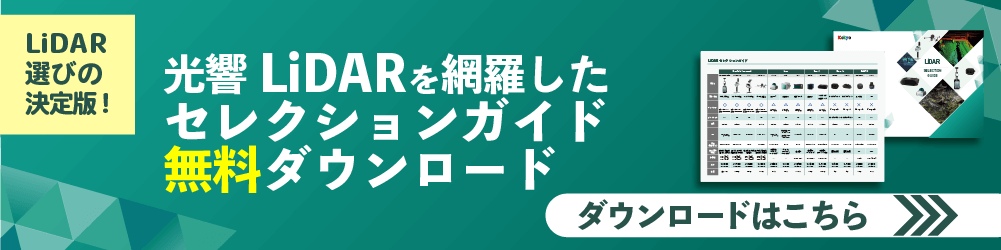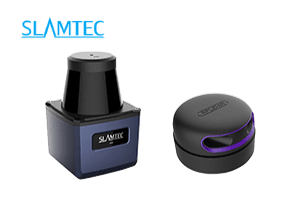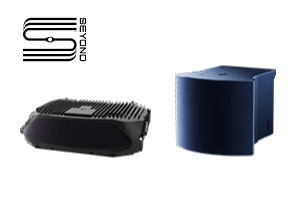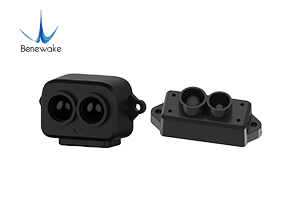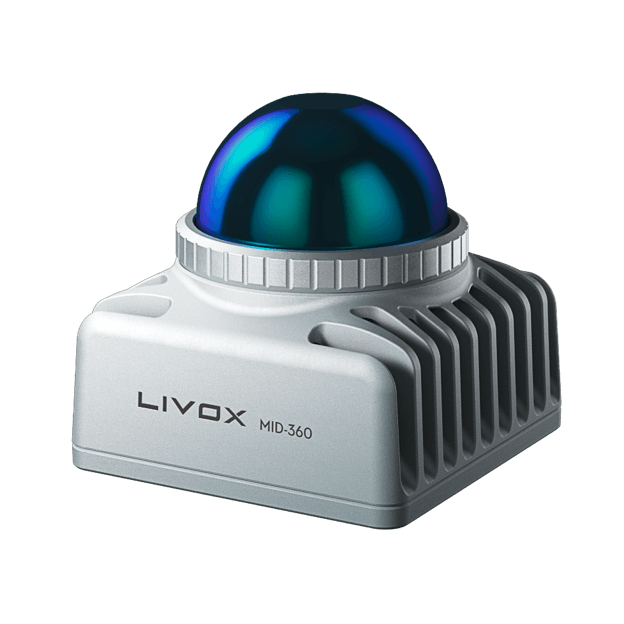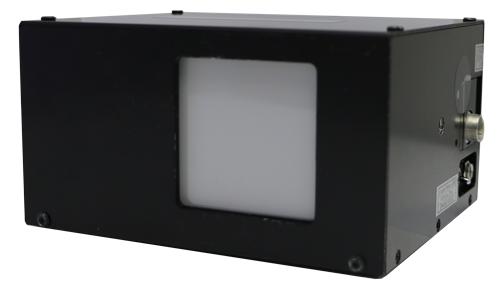センサフュージョン とは
センサフュージョン とは、複数のセンサから得られる情報を組み合わせ、目的に応じた情報処理を自動的に行うことで、人間の判断を支援する技術です。
たとえば、人が視覚や聴覚、触覚といった五感を使って周囲の状況を把握するように、機械もカメラやLiDAR (ライダー)、レーダーなどの異なるセンサを連携させることで、より正確で信頼性の高い環境認識が可能になります。
それぞれのセンサには得意・不得意があり、たとえばカメラは色や形の識別に優れる一方で暗所では性能が落ちます。逆にレーダーは夜間や悪天候でも対象物を検出できますが、詳細な画像認識は苦手です。センサフュージョン は、こうしたセンサごとの特性を活かしながら補い合うことで、単独では得られない高度な判断や制御を実現するのです。
仕組みの種類:3タイプ比較
| 方式 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 集中型フュージョン | すべてのセンサデータを中央のCPUで統合処理 |
・精度が高い ・柔軟な処理が可能 |
・高性能なCPUが必要 ・処理負荷が集中し遅延の可能性 |
| 分散型フュージョン | 各センサが初期処理を行い、その後統合 |
・CPU負荷を軽減 ・リアルタイム性が高い |
・初期処理で情報が失われやすい ・精度はやや低め |
| ハイブリッド型フュージョン | 集中型と分散型を組み合わせた方式 |
・柔軟性と安定性を両立 ・用途に応じた最適化が可能 |
・構成が複雑 ・通信・演算コストが大きい |
使用例
自動運転支援
- カメラ+LiDARで人や障害物を高精度に検出
- NECの監視ソフト
- カメラで人を認識
- 3D LiDARで距離を測定
- AIが姿勢や動作を分析して危険を予測
- 建設機械やフォークリフトにも応用可能
- 作業員の安全確保や事故防止に寄与
MMS(モバイルマッピングシステム)
- 車両にセンサを搭載し、走行しながら3D地図や画像を取得
- 道路調査、トンネル点検、災害対策に活用
- 自動運転向けの「ダイナミックマップ」構築にも使用
- 常に最新の地図データを生成・更新可能
まとめ
- センサフュージョン は、異なるセンサの長所を融合し、単体では難しい高精度な認識を可能にする技術。
- 自動運転支援では、カメラ+LiDAR+AIの組み合わせにより、人的ミスを防ぐ安全支援に特化。
- MMS用途では、3D空間測量とビジュアル情報を統合し、マップ作成や災害対策に利用。
- 将来的にはAIのさらなる活用で、人間の意思決定に匹敵する精度が期待され、IoTやウェアラブル家電などへの応用も進展中。